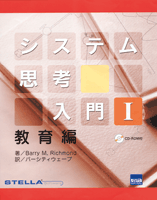
| システム思考入門I |
|---|
| 教育編 |
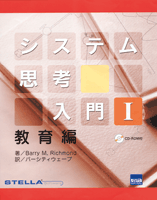 |
| 著者 | Barry M Richmond |
|---|---|
| 訳 | バーシティウェーブ |
| 判型 | B5変型,192頁 |
| 本体価格 3,200円 | |
| ISBN | 4-87783-117-7 C3004 |
本書は isee systems, inc. 社が開発し、日本国内では(株)バーシティウェーブが販売代理店を行なっている、ビジュアルシンキングツールソフトウェア「STELLA」に付属している「Introduction to Systems Thinking」の翻訳書です。本書には、30日間の使用制限付き体験版ソフトウェアと、本書で紹介しているサンプルモデルを含むCD-ROMが付属しています。
--内容から--
■パート1 システム思考の言語
STELLAソフトウェアでモデル、それも良いモデルを作成するという作業は、良い著作物、たとえばショートストーリーや映画の台本、小説などを書くのと良く似ています。また、一般にモデルを作成するより文章を書くことに慣れている人がほとんどのため、本書では、モデル作成という行為を文章を書くという行為になぞらえて、モデルの説明を進めることにしました。この方法により、システム思考のコンセプトやプロセスの理解が早まると期待しています。この理由から、本書の各章においては、ものを書くという作業を軸にして説明を記載してあります。
パート1では、文章の説明と並行してシステム思考について説明します。つまり鉄道のレールに例えると、1本はシステム思考、もう1本は文章ということになります。たとえば、第2章では、話法の基本要素をストックとフローの観点から見ていきます。第3章では、良い文章を作成するのに必要な文法上の規則について説明してあります。第4章では、文と文の接続に関する説明があります。第5章と第6章では、簡単なパラグラフ、また複雑なパラグラフの書き方について説明してあります。最後の第7章では、複数のパラグラフをまとめ、ショートストーリー(短編)を作成する手順を記載してあります。
パート1では文章を例として使って、システム思考の理解を深めます。ここでは、システム思考の3つの主要思考法であるオペレーショナル思考法、閉ループ思考法、非直線的思考法について説明します。
言語(文章)と思考法とは実際、相互に深く関連しています。質の高いショートストーリーを書きたい場合だけでなく、いくつか優れた文を書きたいときでも、言語のほかシステム思考に関する知識もしっかりと理解しておかなければなりません。この両者が備わっていて初めて、良い文章が書けます。
■パート2 ライティングプロセス
パート2の各章では、STELLAソフトウェアを使って「文章を書く」方法を具体的に説明します。まず、第8章では、ライティング(記述)プロセスの概要を解説します。次の第9章では、具体的な例を使いながらライティングプロセスを説明します。最後の第10章では、STELLAソフトウェアを使って文章を書くときのガイドラインを紹介します。
このパート2は、初めから順に読むという使い方のほか、モデルの作成中に必要に応じて開くというように、レファレンスガイドとして使うこともできます。モデルを作っていて問題が起き、先に進めなくなったときには、このパート2に記載されているガイドラインや図、例を参考に問題を解決してください。
| パート1 システム思考の言語 | |
|---|---|
|
第1章
|
システム思考とSTELLAソフトウェア |
| 思考 | |
| コミュニケーション | |
| 学習 | |
| 一般批判 | |
| 思考:メンタルモデルの作成 | |
| 10,000メートル思考法 | |
| 原因としてのシステム思考法 | |
| ダイナミック思考法 | |
| 取り込んだ要素をどのようにして表現するか | |
| オペレーション思考法 | |
| 取り込む要素間の関係をどう表現または定義するか | |
| 閉ループ思考法 | |
| 非直線的思考法 | |
| 思考:メンタルモデルのシミュレート | |
| 科学的思考法 | |
| まとめ | |
| コミュニケーション | |
| 共感思考法 | |
| 学習 | |
| まとめ | |
| 以降の各章について | |
|
第2章
|
名詞と動詞 |
| 名詞 | |
| 動詞 | |
| ストックとフローの区別 | |
| まとめ | |
|
第3章
|
文の作成 |
| 文の定義 | |
| 文法 | |
| まとめ | |
|
第4章
|
文のリンク |
| 文をリンクする2つの方法 | |
| ストックからフロー、フローからフローの2種類のリンクの違い | |
| コネクタ | |
| コンバータ | |
| まとめ | |
|
第5章
|
「単純な」パラグラフの作成 |
| フィールドバックループの定義 | |
| 「単純」フィールドバックループ | |
| 「単純」反作用フィールドバックループ | |
| 減衰テンプレート | |
| ストック調整テンプレート | |
| 反作用フィールドバックループのまとめ | |
| 強化フィールドバックループ | |
| 増殖テンプレート | |
| 複数のループの結合 | |
| まとめ | |
| 【付録】一般フローテンプレート | |
|
第6章
|
「複雑な」パラグラフの作成 |
| パラメータの値の変更 | |
| グラフ関数 | |
| リンクの追加による「複合」フィールドバックループの作成 | |
| 変数パラメータの追加 | |
| フィードバックループのまとめ | |
| 次章について | |
| 【付録】グラフ関数の作成と定義 グラフ関数作成のための手順書 |
|
|
第7章
|
ショートストーリー |
| 「成長と衰退」インフラストラクチャー | |
| 「評価の急下降と暖慢上昇」インフラストラクチャー | |
| 「メインチェーン」インフラストラクチャー | |
| 「属性の追跡」インフラストラクチャー | |
| 「相対的魅力」インフラストラクチャー | |
| パート2 ライティングプロセス | |
|
第8章
|
ライティングプロセスの概要 |
| モデル作成のステップ | |
| モデル作成プロセス | |
| 学習プロセス | |
| 次章について | |
|
第9章
|
例によるライティングプロセスの説明 |
| 問題の定義 | |
| 仮定の定義と検証 | |
| 結論の作成と堅牢性の検証 | |
| まとめ | |
| 次章について | |
|
第10章
|
ライティングプロセスのガイドライン |
| モデル作成プロセス | |
| 仮定の定義 | |
| メインチェーン | |
| キーアクター | |
| 最重要ストック | |
| 仮定の検証 | |
| 結論の作成と結論の堅牢性の検証 | |
| 学習プロセス | |
| コーチングシーケンス(指導手順)を作成するときのガイドライン | |
| まとめ | |
| 【付録】モデルを定常状態に初期化する方法 | |
| 索引 |